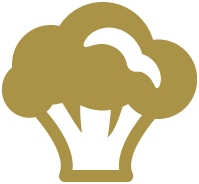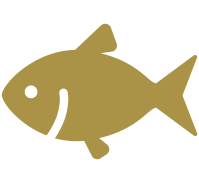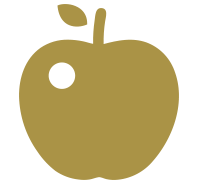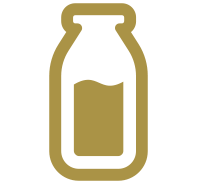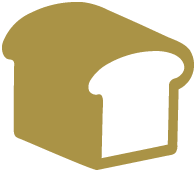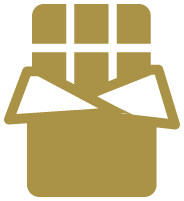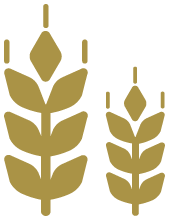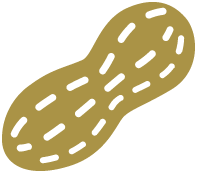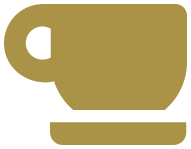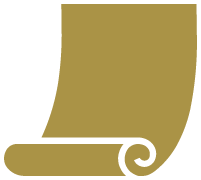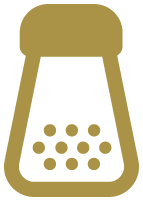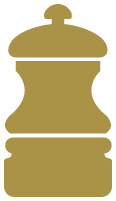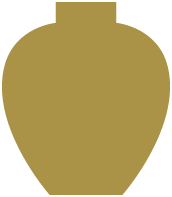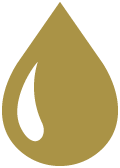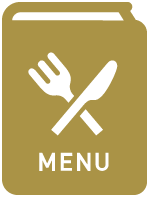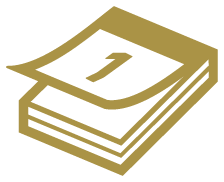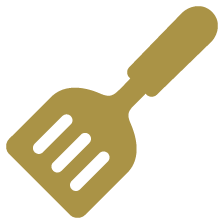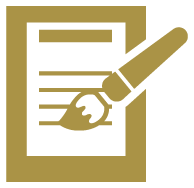当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は1月の歳時記をご紹介します。
【睦月(むつき)】
睦月は1月の別名です。
諸説ありますが、「親戚や知人が互いに行き来し仲睦まじく過ごす月、睦び月(むつびつき)」から転じたとする説が有力です。
その他、「元になる月」→「もとつき」→「むつき」に転じたとする説もあります。
【1月の行事など】
1日:元日(がんじつ)
正月は年神様に豊作を願い、収穫に感謝する古くから行われてきた儀式。
年神様は田の神、山の神、そして我々のご先祖様(祖霊神)です。
「明けましておめでとうございます」は無事に年が明け、年神様をお迎え出来た事を喜ぶ言葉です。
また、初日の出を拝むのは、太陽が年神様の象徴とされてきた事に由来します。
5日:小寒(しょうかん)
寒さの極限一歩手前の頃。
小寒は「寒(かん)の入り」とされ、立春の「寒の開け」まで約一ヶ月を「寒」といい、一年のうちで最も寒い時期がやってきます。
また、小寒から大寒に出すのが「寒中見舞い」です。
※松の内を過ぎた1月8日~立春前日の2月3日までや、1月15日以降など、地域や考え方によって様々です。
7日:人日の節句(じんじつのせっく)
五節句のひとつ。
人日とは「人の日」という意味で、1月7日に七種類の野菜を入れた汁物を食べ、無病息災などを願った、中国の風習に由来します。
日本では平安時代に七種類の穀物を使った粥を作るようになり、その後日本古来の風習である「若草摘み」と結びつき、鎌倉時代に今のような七草を入れた粥を食べるようになりました。
現在はスーパーなどで七草粥セットが売られていますが、昔は前日に七草を摘み、刻んで水にさらしておき、当日の朝、粥を炊きました。
※春の七草:芹(セリ)・薺(ナズナ)・御形(ゴギョウ)・繁縷(ハコベラ)・仏の座(ホトケノザ)・菘(スズナ)・蘿蔔(スズシロ)←スズナはカブ、スズシロは大根の事
1~7日(関西地方は~15日が多い):松の内
門松や松飾りを飾っておく期間。
飾りはこの期間が終わると外され、翌日8日(地方によって異なる場合も)に行う「どんど焼き」で燃やし、年神様を天に送ります。
書初めを一緒に燃やし、燃えかすが天高く舞うと字が上達するという言い伝えがあります。
「どんどや」と言いながら燃やすので、「どんど焼き」と呼ばれるようになったとされています。
11日:鏡開き(かがみびらき)
年神様にお供えしていた鏡餅をいただく日。
年始に固くなった餅をいただき、歯の健康を祈る「歯固め」の意味もあります。
お汁粉や雑煮、かき餅などにします。
鏡開きの餅は包丁を使わずに木槌や手で割ります。
これは、年神様が刃物を嫌うと考えられていたためで、縁起を担いで「開く」と表現します。
松の内が7日の地域は11日、15日の地域は15日に行う事が多いです。
11日:成人の日
新成人を祝う国民の祝日。
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」とされています(内閣府HPより抜粋)。
成人を祝う風習は古く、武家の「元服の儀」に由来します。
小正月に行われていた事から15日に制定されていましたが、現在は毎年第二月曜日です。
15日:小正月(こしょうがつ)
旧暦よりもっと前の時代の正月は旧暦の1月15日に当たるため、旧暦では1日を「大正月(おおしょうがつ)」、15日を「小正月」としました。
1日は年神様を迎える行事、15日は家庭的な行事を中心に行います。
小正月は小豆粥をいただき、無病息災を祈ります。
小正月をもって正月行事が終わるので、「正月事じまい」として松の内を15日までとする地域があります。
20日:大寒(たいかん)
一年で最も寒さが厳しいくなる頃ですが、季節は徐々に春に向へとかいます。
【1月の味覚】
大根・かぶ・ゆりね・小松菜・水菜・金柑・伊予柑
伊勢海老・赤貝・公魚(わかさぎ)・寒しじみ・河豚・子持ち鰈など
【おせちの三つ肴と雑煮の意味】
おせち料理は「節供料理(せちくりょうり)」の略で、五節句の際にお供えする物でしたが、次第にお正月にいただく料理を指すようになりました。
基本的に縁起を担いだ内容になっていますが、他がなくてもこれだけ用意すれば良いとされる料理があります。
それが「おせちの三つ肴」、黒豆(まめに働き、まめに暮らせるように)・数の子(子孫繁栄)・ごまめ(豊作を祈って)です。
関西地方ではごまめがたたき牛蒡(根を深く張り家が代々続くように・たたいて開運を願う)に変わります。
※黒豆の意味に使われる「まめ」は丈夫・健康を意味する言葉です。
雑煮は年神様の年魂(としだま)をいただくための料理です。
餅は米を使っており、稲の霊が宿る食べ物とされ、神様の生命力を分けてもらえる縁起の良いものです。
お供えしていた餅と一緒に、その土地で採れるもの、作られるものを入れて頂くので、地域ごとに様々な雑煮があります。
いよいよ新しい年の幕開けです。
皆さんにとって良い年となるよう、お祈りいたします。
Text by さゆり/食育インストラクター
-
カテゴリ