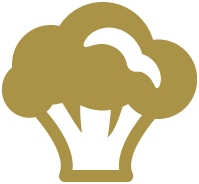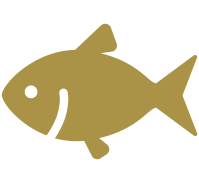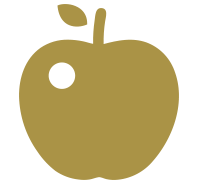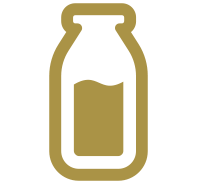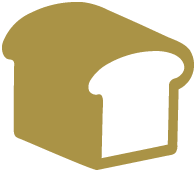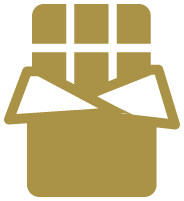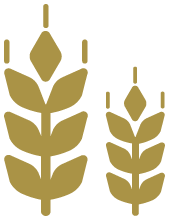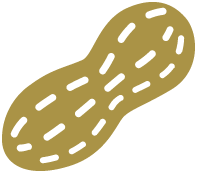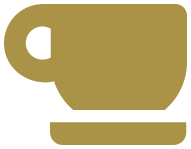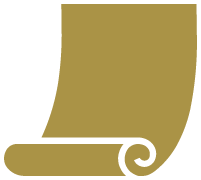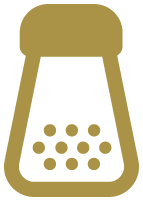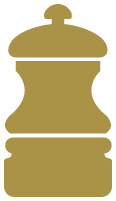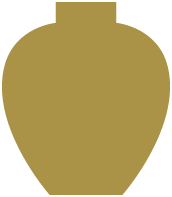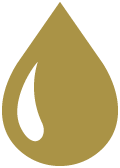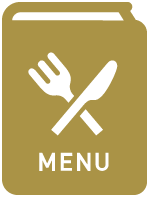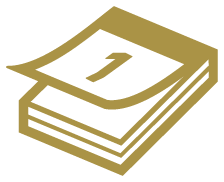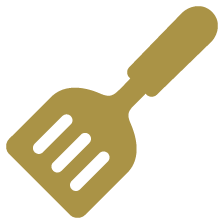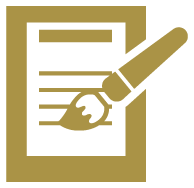保存性が高く、栄養も豊富な豆は、料理やお菓子だけでなく、しょうゆ・味噌などの加工品の原料としても使われ、私たちの食生活に欠かせません。 さらに、縁起を担ぐお正月の「黒豆」や邪気を払う節分の「炒り大豆」など、行事でも豆は大切な役割を持っています。 世界にはマメ科の植物が約1万8千種もありますが、そのうち食用とされているのは約70種。今回はそのなかから代表的な豆類4つをご紹介します。
【豆の代表的な種類】
■大豆
大豆は、「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価が高い食材として知られています。
豆腐をはじめ、納豆や味噌、しょうゆなどの原料としてよくみかける「黄大豆」のほか、郷土料理のひたし豆やうぐいすきな粉に使われる「青大豆」、おせち料理に欠かせない黒豆の煮物に使われる「黒大豆」などがあります。
■小豆
小豆の赤い色には神秘的な力があると古くから信じられており、古くから魔除けやお祝いごとに用いられてきました。
普通の小豆より粒が大きいものを「大納言」と呼んでいます。大納言は皮が破れにくく煮崩れしにくいことから、粒をいかした和菓子によく使われています。小豆とは別種ですが、見た目がよく似たものに「ささげ」があります。
■いんげん豆
豆類のなかで品種が豊富で世界中で日常的に食べられている豆のひとつです。
色や大きさ、柄が多様で、豆全体が真っ白な「白いんげん豆」、鮮やかな赤紫色の「金時豆」、うずらの卵のような模様がある「うずら豆」、虎の毛皮のような模様がある「虎豆」などがあります。
■えんどう豆
乾物としてはなじみがないかも知れませんが、さやえんどう、スナップえんどう、グリーンピースと同じ品種です。
乾燥豆には煮豆やうぐいすあんなどに使われる「青えんどう」、豆大福や蜜豆などに使われる「赤えんどう」が日本では一般的です。
【乾燥豆の基本的な茹で方】
1.豆をサッと洗い、4倍程度の水に浸して一晩おく。(ふっくら膨らみ、皮にしわがなくなるまで)
※豆によっては水に浸す必要のないものもあります。
2.浸した水ごと鍋に入れ、中火~強火にかける。
沸騰したらザルに上げ、茹で汁を捨てる。
3.鍋に豆を戻し、たっぷりと水を注いで強火にかける。
沸騰したらアクをとり、落し蓋をして弱火で茹でる。
※途中、茹で汁が少なくなったら差し水をして水面から豆が出ないように気をつけてください。
4.指で豆をつまみ、簡単に中心まで潰れたら茹で上がりです。
※小豆など小さな豆は40分、いんげん豆など大きな豆は1時間程度が茹で時間の目安です。
最近では、いろいろな種類の豆の水煮が出回っています。
茹でるのは面倒と思う方も、そちらを活用し、おいしくて体にもよい豆料理を楽しんでください。
Text by まち/食育インストラクター
-
カテゴリ