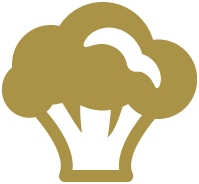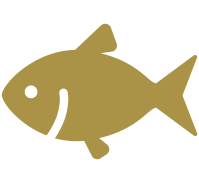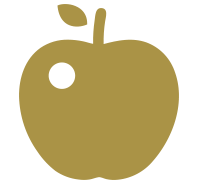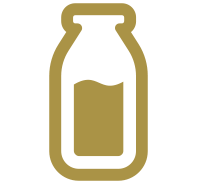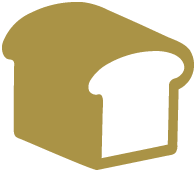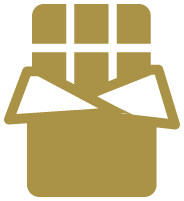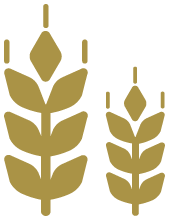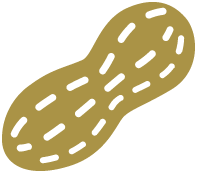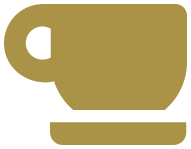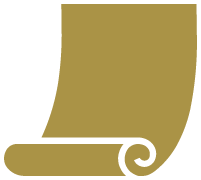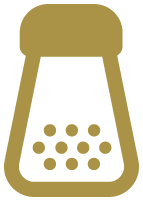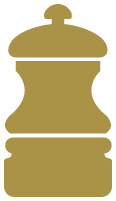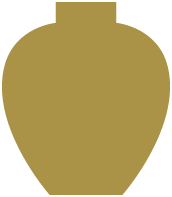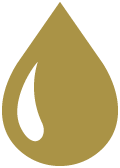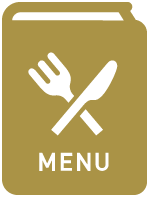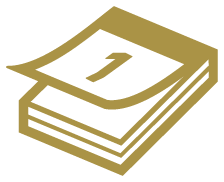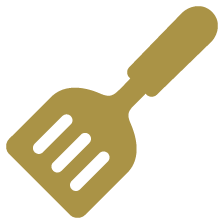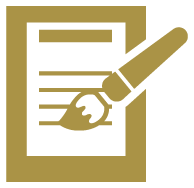年が明けてお正月が過ぎると、お供えしていた鏡餅をいただく鏡開きがやってきます。なぜ鏡開きといわれ、お餅を食べるのでしょうか。
【鏡開きとは】
日本には古来より、新年に五穀豊穣などをもたらし、田や山の神としても崇められている年神様を迎えるお正月があります。
鏡開きはお正月の間、年神様にお供えしていた鏡餅を下げていただく事で、年神様の力を分けてもらい、幸福で平和な一年になるようにと願う行事です。
なぜ鏡開きという名前になったのかというと、鏡開きの「鏡」は、神様が鏡に宿ると信じられていた事、そして稲作文化の日本では米はとても神聖な食べ物であったため、その米を使って作る餅を丸鏡に似せた事に由来します。
「開き」は年神様が刃物を嫌うという考えのもと、いただく際に包丁等を使わず木槌や手で割っていた事から、縁起の良い「開く」という表現になりました。
鏡開きは元々1月20日に行われていましたが、三代将軍徳川家光公の月命日が20日だったため、松の内が1月7日までの地域は11日に、1月15日までの地域は15日に鏡開きを行うようになりました。
【真空パック鏡餅はどう開く?】
鏡餅を開く(割る)というのは、手作りの鏡餅が時間とともに乾燥し、固くなってしまうので行われていた方法です。しかし、現在は鏡餅の形をした真空パックに餅が充填された商品や、個包装になった餅が入った商品等を購入して飾る方が多いと思います。
水分が多い状態の餅を木槌や手で開くのは難しいので、意味を知った上でけがをしないように気を付けながら包丁等を使って開いて下さい。
【鏡餅のいただき方】
昔ながらのいただき方は、雑煮やお汁粉ですが、おかゆに入れたり、かき餅にするというのも美味しいです。
かき餅は、小さく切ってしっかり乾燥させた餅を油で揚げ、熱いうちにしょうゆをかけたり、塩を振って冷まします。手作りのかき餅はカリッと香ばしく、子どものおやつにぴったりですね。
様々な風習が時代と共に簡素化されていますが、その風習がどうして始まったかを知り、後世に繋げていく事は私達の国を知る上でとても大切です。
ぜひ、行事についてたくさんの人とシェアーしてください。
Text by さゆり/食育インストラクター
-
カテゴリ