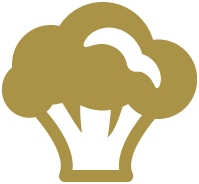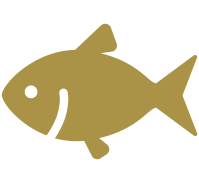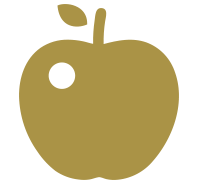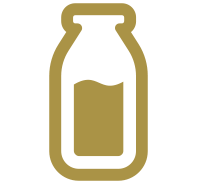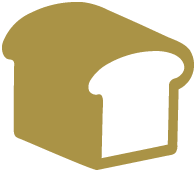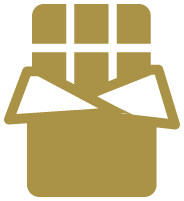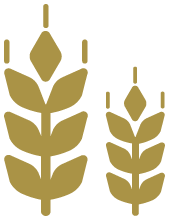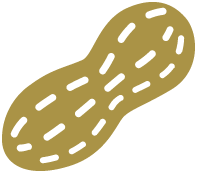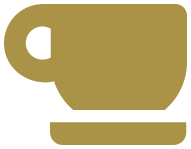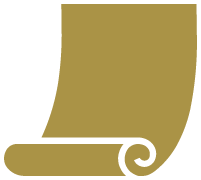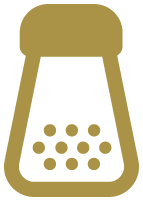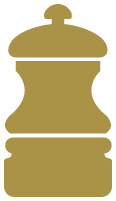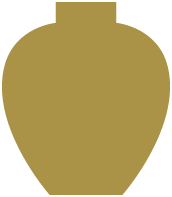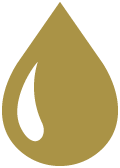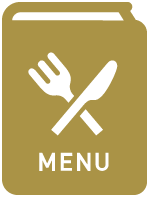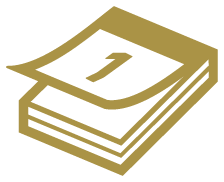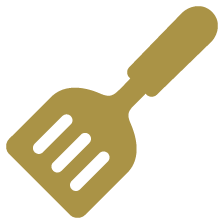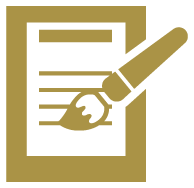夏至や冬至、春分や秋分といった言葉。カレンダーにも記されているので、一度は見たり、聞いたりしたことがあるでしょう。これらは「二十四節気」と呼ばれています。 二十四節気にはどのような意味が込められ、私たちの食とどのように関わっているのでしょうか。
【二十四節気とは?】
二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を約15日ずつ、24個の季節に分けたもので、飛鳥時代に中国から日本に伝わりました。
1つ1つにその時期の動植物の動きや天候を表す言葉がつけられ、農業や暮らしの目安として取り入れられるようになりました。
二十四節気をさらに3つに分けたものが「七十二候」です。七十二候も中国から伝わりましたが、江戸時代に日本の気候風土に合うように幾度も改定され、より微妙な季節の移ろいが示され、生活の中に根づいていきました。
【二十四節気一覧】
<春>
立春(りっしゅん)…春の兆しが感じられてくるころ
雨水(うすい)…雪解け水が流れ出すころ、農耕の準備をはじめるころ
啓蟄(けいちつ)…陽気にさそわれ土の中の虫が動き出すころ
春分(しゅんぶん)…昼夜の長さが同じになる日
清明(せいめい)…すべてのものが清らかで生き生きするころ
穀雨(こくう)…穀物をうるおす春の雨が降るころ
<夏>
立夏(りっか)…夏の兆しが見え始めるころ
小満(しょうまん)…植物が茂り始めるころ
芒種(ぼうしゅ)…穀物の種まきや田植えをするころ
夏至(げし)…一年の中で太陽の位置が高く最も昼が長い日
小暑(しょうしょ)…梅雨が明けて本格的に暑さが増してくるころ
大暑(たいしょ)…一年で最も暑さが厳しいころ
<秋>
立秋(りっしゅう)…秋の兆しが見え始めるころ
処暑(しょしょ)…朝晩涼しく感じ暑さが少し和らぐころ
白露(はくろ)…大気が冷え、朝晩の草花に露が降りるころ
秋分(しゅうぶん)…昼夜の長さが同じになる日
寒露(かんろ)…朝晩が冷え込み、草花の露がより冷たくなるころ
霜降(そうこう)…朝晩の冷えがさらに強くなり、霜が降り始めるころ
<冬>
立冬(りっとう)…冬の始まり、冬支度をはじめるころ
小雪(しょうせつ)…雪が降り始めるころ
大雪(たいせつ)…雪が激しく降り積もり、本格的に冬が到来するころ
冬至(とうじ)…一年の中で太陽の位置が低く最も昼が短い日
小寒(しょうかん)…寒さが厳しくなるころ
大寒(だいかん)…1年で最も寒さが厳しいころ
【二十四節気と食文化】
日本には、無病息災を祈ったり、穢れを祓ったりと、行事のときにはその時に合わせた行事食をいただきます。
それと同じように二十四節気にもその季節にあった料理や食材を食べる風習があります。今回はその中から3つご紹介します。
■冬至
「ん」がつくものを食べると運が呼び込めると言われ、「なんきん(かぼちゃ)」や「れんこん」などを使った料理が食べられています。
縁起を担ぐだけでなく、寒い季節を乗り切るために旬の食材を食べ、栄養をつけるといった意味もあります。
■夏至
夏至に全国的に食べられているものは特にありませんが、夏至の期間中である6月30日に行われる「夏越の祓」には、水無月(外郎生地に小豆をのせた和菓子)を食べる風習があります。氷の形で暑気を払い、上にのった小豆は厄除けの意味が込められています。
■春分・秋分
春分の日には「ぼたもち」、秋分の日には「おはぎ」が食べられています。これば、ご先祖様にお供えし感謝を伝えるとともに、それをいただくことでご先祖様や神様の力を取りこむという意味があるとされています。
これだけでなく、二十四節気に合った旬の食材を使って料理をするなど、身近なところでも季節を感じることができます。
二十四節気を通して、美しい日本の春夏秋冬の移り変わりを景色だけでなく、食事でも楽しみ、今年一年もよい年になるように過ごしましょう。
Text by まち/食育インストラクター
-
カテゴリ