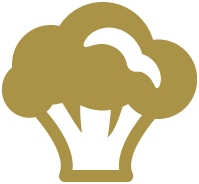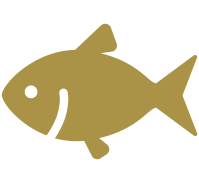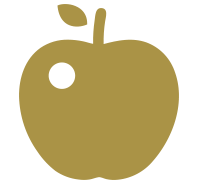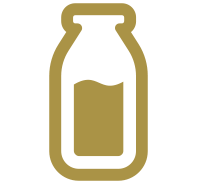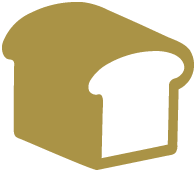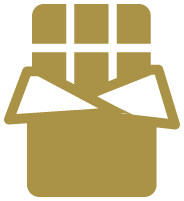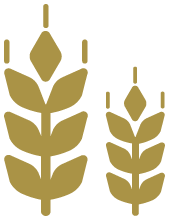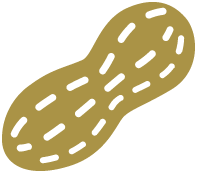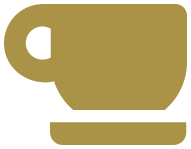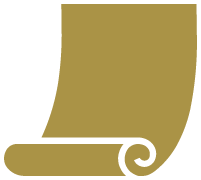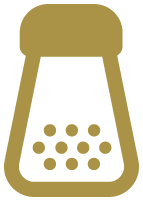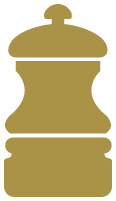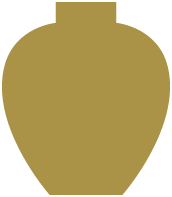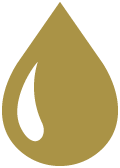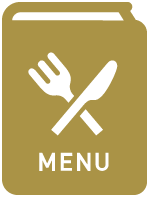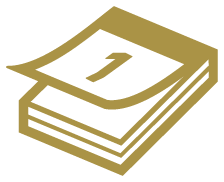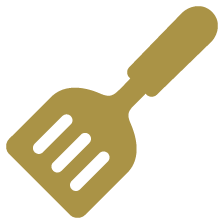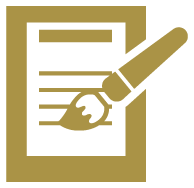現代の日本人にもっとも身近な小豆といえば、和菓子などの甘い食べ物をイメージされることが多いのではないでしょうか?
【邪気払いにも!?縁起のよい食材「小豆」】
あんこは大変おいしい食べ物ですが、小豆はあんこだけではなく、赤飯などの縁起物として登場することも多い食べ物です。
また、邪気を払う効果があると考え、小正月に小豆粥を食べる風習もあります。旧暦の1月15日は立春後最初の満月の時期で、この日に食べられる小豆粥は望(もちがゆ)とも呼ばれます
文献では土佐日記の中に小正月に小豆粥を食べていた様子が記されています。さらに文献をさかのぼると、古事記の中で五穀豊穣の五穀として数えられている穀物のひとつに小豆があり、日本人との付き合いの長さをうかがわせるとともに、それだけ古くから縁起の良いものだと考えられていた食べ物なのが分かります。
一説によると、春秋の彼岸に牡丹餅(おはぎ)を食べる理由も、縁起良く、邪気を払う小豆のお菓子だからではないかとも言われています。
【小豆とささげの違いとは?】
ちなみに、主に関東地方で赤飯を炊くときに使われる、ささげという良く似た豆があります。小豆とささげ、どちらもササゲ科の豆で、親戚のような関係です。
小豆を煮て皮が破れたものは、「腹を割く=切腹」のイメージがあり、武家社会の関東では皮が破れにくいささげの赤飯の方が好まれたとの説があります。
【小豆の嬉しい効能】
そんな小豆は、栄養価も豊富な豆のひとつで、余分なナトリウムを排出させるカリウムが豊富です。
そのほか、ポリフェノールのサポニンも含まれるため、体のさびつきを防ぎ、健康に役立つ効果が期待できます。水溶性の栄養素が多く含まれるので、小豆の煮汁を有効活用できる赤飯などは効率的に栄養を摂取できるレシピと言えそうです。
なお、これまでは小豆の赤い色はポリフェノールのアントシアニン色素に由来しているものだと考えられてきましたが、近年の研究では全く新しい色素成分ではないかとする論文が発表されています。
まだまた神秘に満ちた存在であるところも、小豆の魅力のひとつなのかもしれませんね。
Text by はむこ/食育インストラクター
-
カテゴリ