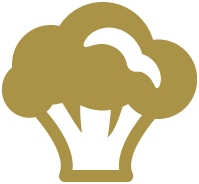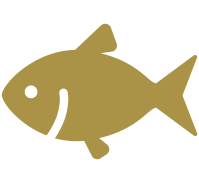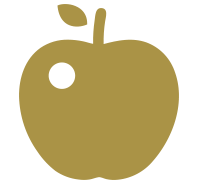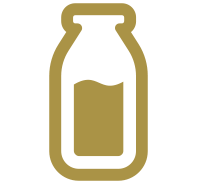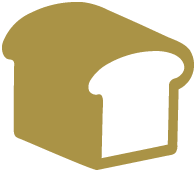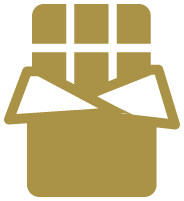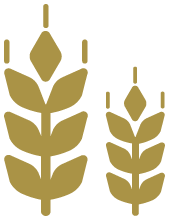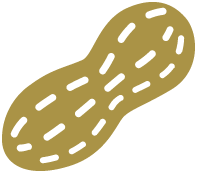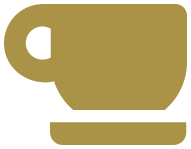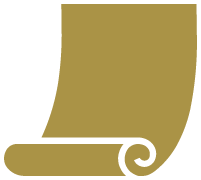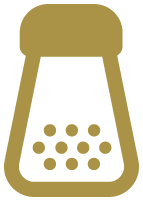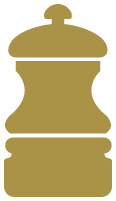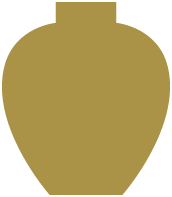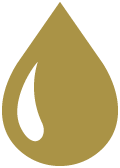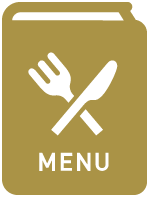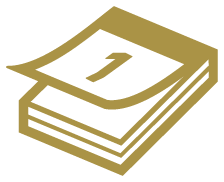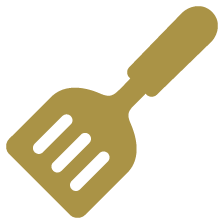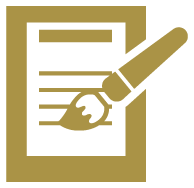日本の行事は中国から伝来し、その後、独自に変化したものがたくさんあります。 中でも「五節句」は特別な行事として、今でも多くの人が大切にしています。そこで、今回は覚えておきたい五つの節句についてご紹介します。
【節句とは】
「節(せつ)」は、唐時代の中国で定めた季節の節目を意味する言葉です。
その当時、中国では奇数の重なる日に邪気を払う儀式を行っていました。それが日本に伝来すると、日本古来の風習と結びつき、独自の行事となりました。
「節句」は本来、無病息災を祈り、供え物をするので「節供」と書いていましたが、のちに現在の「節句」へと変化しました。
【五節句】
五節句にあたる行事は、もとは宮中の祭事です。
しかし、江戸時代に五節句が制定され、式日(祝日の事)となると、次第に庶民に広まっていきました。明治時代に旧暦から新暦に変わると、五節句自体は廃止となりましたが、現在でも年中行事として国民の間に定着しています。
以下が五節句です。
●人日の節句(じんじつのせっく) 1月7日
その年の無病息災を願う日です。
行事食として七草粥をいただきますが、正月の祝膳などで疲れた胃腸を労わり、不足しがちな青菜をとるという知恵もあるそうです。
●上巳の節句(じょうしのせっく) 3月3日
「桃の節句」ともいわれます。
「ひな祭り」として女の子の成長を祝う日というイメージが強いですが、もともとは年齢や性別を問わず、人々の幸せを願い、邪気を払う行事でした。
●端午の節句(たんごのせっく) 5月5日
中国の菖蒲を使った邪気払いの行事が起源です。それが日本の「早乙女の神事」という菖蒲を使った行事と結びつき、広がりました。
その後、武家社会の「勝負」・「尚武」に通じるとして、男児の成長を願う日へと変わり、長い時を経て、昭和23年に男女問わず子ども達の幸せを願う「こどもの日」となりました。
●七夕の節句(たなばたのせっく) 7月7日
中国の七夕伝説と日本の風習が結びつき生まれた行事で、その中に出てくる「棚機(たなばた)」にあやかり、「七夕(しちせき)」を「たなばた」と読むようになったのだそうです。笹や竹に願い事を吊るす風習は、習い事をする子どもが増えた江戸時代に始まりました。
●重陽の節句(ちょうようのせっく) 9月9日
別名「菊の節句」ともいわれる長寿や繁栄を願う行事です。
昔は五節句を締めくくる行事として、盛大に行われていました。「お九日(おくんち)」とも呼ばれ、長崎・佐賀・福岡のお祭り「くんち」とも関わりの深い節句です。
いかがでしたか。
日本の四季ともかかわりの深い行事ですので、覚えておくと役立つ事があるかもしれませんね。
Text by さゆり/食育インストラクター
-
カテゴリ